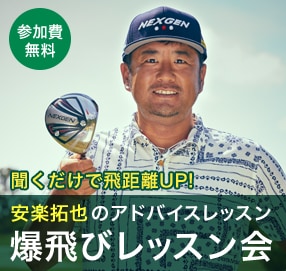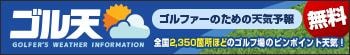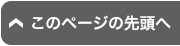かつてクラブを組む際は、接着剤を用いてヘッドにシャフトを装着するのが一般的で、基本的に、シャフト交換をした後で細かな調整をすることはできなかった。しかし、テーラーメイドの『R9 ドライバー』が登場して以降、シャフト先端にスリーブをつけ、ネジで脱着する“カチャカチャ”を採用するドライバーが主流となった。
メーカーなどによって細かな違いはあるが、『カチャカチャ』が搭載されたドライバーは、シャフトにつけられたスリーブの向きを変えるだけで「ロフト角」、「ライ角」、「フェースアングル」といった要素を調整することができる。それまで、いちいちシャフトを脱着しなければできなかったクラブの微調整がレンチひとつでできるようになったのはゴルファーにとって大きなメリットだろう。
トッププロのドライバーを見ていくと、カチャカチャによる調整がきっちり利用されていることが分かる。たとえば、テーラーメイド『ステルスプラス ドライバー』を使用するローリー・マキロイ(北アイルランド)は、スリーブの「LOWER」の方向に回し、ロフトを立てる調整をしている。
誤解している方がいるかもしれないが、カチャカチャを使った調整では、ピンポイントにロフトだけを変えるといった調整はできず、複合的にいくつかの要素が変化する。マキロイの「LOWER」にする調整では、ロフトを立てるとともに、フェースアングルが「オープン」に、ライ角が「フラット」に変化するのだ。
米国男子ツアーのプロたちは、こういった特性を理解した上で、思い切り叩いても、引っかけない調整をしているプロが多い。性能的な問題だけでなく、そもそも本人が「構えやすい」と感じる顔に調整している可能性もあるだろう。何にせよ、カチャカチャは特性を理解した上で利用すれば、より使い勝手の良いクラブを手にすることができるわけだ。
一方で、アマチュアゴルファーの多くは、カチャカチャをほぼ使っていないといわれている。自分に適した調整が分からないといった理由があると考えられるが、カチャカチャによって何が変化するのかを理解できていないことが大きいだろう。
というのも、シャフトのスリーブには、先ほどの「LOWER」をはじめ、「ドロー」、「フェード」といった球筋を表す単語がよく用いられている。確かに、調整を加えることで表記の球筋が出やすくなるだろう。しかし、人によっては「ドロー」に調整したことで逆球が出る可能性もある。
つまり、カチャカチャを「弾道調整機能」と考えると、違和感や不信感を抱き、結果、使用が遠のくという結果になってしまうのだ。カチャカチャはあくまで、インパクトでフェースをスクエアかつ、狙った打ち出し高さのボールを打ちやすくするためのフィッティング的な調整機能。フェードを打ちたい人に「ドロー」の調整が合うことも多いし、ドローヒッターが左への曲がりすぎを防ぐために「フェード」にする必要がある場合もあるわけだ。
このようにカチャカチャは手軽にクラブが調整できる便利な機能だ。「ドロー」であれば、ロフトが寝て、ライ角がアップライトになり、フェース角は閉じ気味になるなど、ヘッドにどのような変化が生まれるのかをしっかり理解して利用できれば、ショットの曲がりが減って、効率的に飛ばせるようになるだろう。(文・田辺直喜)
<ゴルフ情報ALBA.Net>