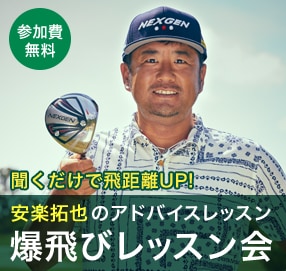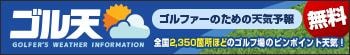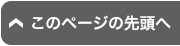<関西オープン 最終日◇26日◇KOMAカントリークラブ(奈良県)◇6979ヤード・パー72>
大槻智春のツアー初優勝で幕を閉じた今年の「関西オープン」。星野陸也との4ホールに及ぶプレーオフを制しての勝利だったが、プレーオフの舞台になった18番パー4についてどう思っただろうか。
激闘を制し誇らしげにカップを掲げる大槻智春【写真】
ティイングエリアから打ち下ろしになっていて、フェアウェイ左サイドには池が、グリーン右手前と左手前には深いバンカーが待ち構えている。初日と2日目は一番後ろのティイングエリアを使っていたので、グリーン中央までは389ヤードあったが、3日目と最終日の決勝ラウンドでは、今回新たに前方につくったティイングエリアを使用したため、325ヤードと距離が短くなっていた。なぜわざわざ決勝ラウンドだけティイングエリアを前に出したのかといえば、選手にドライバーで1オンを狙ってほしかったからだ。
確かに1打を争う緊迫した場面で、追いかける選手が1オンを狙って一発逆転のシーンが生まれたならば、ギャラリーは大いに盛り上がるだろう。その考え自体は悪くない。だったら、325ヤードという数字は中途半端ではないか。これでは飛ばし屋の選手にしか1オンのチャンスはない。無理に狙って力んだ結果、左の池につかまるリスクを考えれば、ティショットを刻む選手も出てくるだろう。
実際、刻んでいた選手も少なくなかった。「いや、優勝した大槻は果敢に1オンを狙ってティショットを花道まで運んだじゃないか。しかもバーディを奪って首位の星野に追いついた」と思う人もいるだろう。しかし、それは2打目のアプローチが成功しただけで、本来の狙いとは異なる。せっかく1オンを狙わせるためにティイングエリアを前に出すのであれば、あと10ヤードほど距離を縮めてもよかったのではないか。打ち下ろしも計算して、グリーンまでが290ヤードぐらいなら、どの選手にも1オンのチャンスが生まれてくる。飛ぶ選手は3番ウッドを使えばいいだけだ。残念ながら最終日はだれも1オンに成功することはなかった。
単純に距離を短くしたからといって簡単になるわけでもない。直接グリーンにボールを落とせば、奥まで跳ねて転がっていくリスクもある。難しいアプローチが残ってしまうだけに、しっかりと花道に落とすコントロールが要求されるのだ。そういうことを乗り越えて1オンに成功した選手には、しっかりとイーグルのチャンスを与えればいい。18番ホールには最も多くのギャラリーが集まっていただけに、さぞ盛り上がっただろう。
何かの事情でたとえ10ヤードでも短くできないのなら、それでも構わない。だったら、ピンポジションをもう少し考えるべきではなかったか。今回は初日から多くのホールで傾斜にばかりカップが切られていた。いいショットを打っても、それが報われない場面が少なくなかったのは確かだ。18番ホールにしても例外ではなく、そう簡単にパットを入れたり、寄せ切れる位置にピンは立っていなかった。
最終日、大槻と星野はプレーオフも入れると、18番をそれぞれ5回ずつプレーしたことになる。しかし、バーディを奪ったのは2人合わせて2回しかない。優勝争いというプレッシャーがあったにせよ、17番までに大槻は6個、星野は9個のバーディを奪っていた。にもかかわらず、バーディを簡単に奪えなかったのは、ピン位置に理由があったのではないか。仮に、もう少し距離を短くしておけば、また違ったプレーオフが見ることができたかもしれない。
ちなみに、1オンを狙えるパー4のホールはほかのトーナメントでもある。例えば、「ダンロップ・スリクソン福島オープン」では、9番ホールが打ち下ろしになっており、日によってはティイングエリアを前に出し、1オンを狙えるようにしている。この試合では、主催者でもあるJGTO(日本ゴルフツアー機構)がピン位置を決定しているので、極端な傾斜に立っておらず、1オンに成功した選手がイーグルを奪う場面も珍しくない。それを知っているのか、毎年最終ホール並みにギャラリーが集まってくる。
今大会でのプレーオフでも、それこそイーグルで決着をつけたとなれば、より注目度が高まったはず。単純に結果だけ見た人は、短いホールでバーディをとれないのはなぜ? と感じたのではないか。技術が足りないといわれたらそれまでだが、勝った大槻も、敗れた星野も素晴らしいドライバーショットを放ち続けていた。それを生かし切れるようなセッティングではなかったことが残念でならない。(文・山西英希)
<ゴルフ情報ALBA.Net>