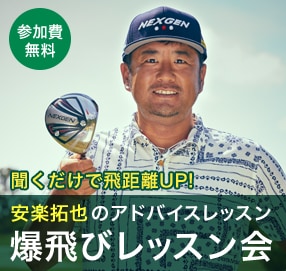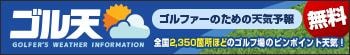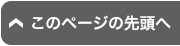圧巻の8打差大逆転。「デサントレディース東海クラシック」最終日は、渋野日向子のひとり舞台となった。申ジエ、テレサ・ルー、上田桃子、イ・ミニョンらの実力者たちを撃破しての国内ツアー3勝目。「全英AIG女子オープン」優勝以来、初めての勝利にトレードマークの笑顔が弾けた。
これで、さらに“シブコフィーバー”の効果はさらに持続することになる。だが、これをツアーはどれだけ今後につなげることができるのだろうか。
渋野の全英優勝以降、日本の女子ツアーの人気沸騰は目を見張るものがある。試合会場に直接足を運ぶギャラリーはもちろん、テレビ中継の視聴率も悪くない。スポーツニュースやワイドショーでとりあげられる頻度も多く、これまでのゴルフファン以外の間でも“シブコ”の名は広まっている。これを一過性のものにしないためにはどうしたらいいのか。
振り返れば、1987年に岡本綾子が外国人として初めて米女子ツアー賞金女王となった後の“綾子フィーバー”に始まり、アマチュアでツアー優勝を飾った宮里藍の爆発的な人気は、いずれも日本の女子ゴルフを世間に知らしめた。宮里以降、ジュニア出身の若手が入れ替わり立ち代わり活躍していることから、ツアーは一定の人気を保っている。だが、それはあくまでゴルフファンの間だけでのこと。さらに広がるまでには至らなかった。
一体なぜか。ここを突き詰めていくと、人気を継続的なものにして、さらに広げようとするツアーの努力が足りなかったということになる。
小林浩美会長は、就任以来ずっと「世界に通用する選手を育てる」と公言してきた。そのため、渋野が全英で優勝すると、それが形になった、と笑顔で口にした。だが「24試合で生涯獲得賞金1億円突破」と、今回の優勝で報じられた通り、渋野がプロになってから出場したレギュラーツアーは24試合(プロテスト合格前に単年登録選手として出場した2018年アース・モンダミンカップを含む)。昨年プレーしたステップ・アップ・ツアー16試合とあせても40試合に過ぎない。ここで経験を積んだのは確かだが、メジャータイトルを手にするほどに羽ばたく土壌は、むしろプロ入り前にあるのではないか。
ジュニア育成という部分では、ツアー会場でジュニアイベントを行ったり、「あこがれの選手」として、それぞれのプロが子どもたちの目標になるという基本的なことはしてきたかもしれない。ジュニア育成を後押ししたティーチングプロもいるだろう。だが、ゴルフとは縁のない育ち方をした子供たちにも目標にしてもらうように人気を継続させる、というようなことが行われてきただろうか。答えは…。
試合ごとに異なる主催者が、それぞれの思惑で大会を盛り上げる。そう書けば聞こえはいいが、LPGAとしては“主催者に丸投げ”という言いかたもできる。テレビ中継もそれぞれ違うものを欲しがるから、取材の際などには選手にとっては二度手間、三度手間の状況が続くことだってある。最大の財産である選手のPRに力を入れるということをもっと真剣に考える必要もあるだろう。
このめんどうから選手を守りつつ、各メディアのニーズを守るというバランスを取る。その上で継続的にツアー、選手をPRする。もちろん、より多くの人に現場に足を運んでもらい、コアなファンを増やしていく。組織として当たり前の広報活動が、一般の人にも女子ゴルフを広めることに他ならない。
“オイシイとこ取り”ではなく、長い目で見てツアーを育てる。それには、選手のレベルを上げるだけでなく、ファンを増やし、応援し続けてもらう努力も含まれている。それを決して忘れないことこそ、シブコ効果の継続につながる。(文・小川淳子)
<ゴルフ情報ALBA.Net>