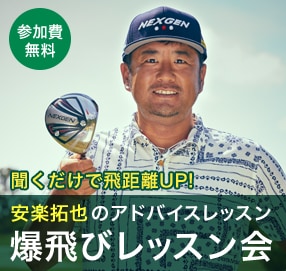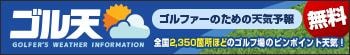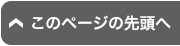一般アマチュアゴルファーは、同じ40m/s程度というヘッドスピードが近い理由で女子プロを参考にした方が良いと言われているが、参考できるのはスイングだけではない。女子プロたちも我々アマチュアと同じように「球が上がらない」など多種多様の悩みを抱えていて、それを矯正しているのは、スイングだけでなく14本のクラブたちなのである。
注目プロ67人のセッティングをひとまとめ!ウェッジ構成も丸わかり!【フォトギャラリー】
そこで、女子プロたちがクラブセッティングにしている、ちょっとした工夫=スパイスをピックアップ。クラブ選びの参考にしてきたい。今回は女子プロたちのウェッジ4本体制について。
ここ数年急激に伸びているのがPWを含めたウェッジ4本体制。飛距離の出る米ツアー勢が下の番手を厚くすることを狙いとしていることが多いが、PW以外の3本ウェッジの構成は様々。この波は近年女子ツアーにも押し寄せている。
「CAT Ladies」で初優勝を挙げた淺井咲希のように、近年のアイアンのストロングロフト化からPWの穴を埋めるべく48、52、58度という組み合わせが多い一方で、鈴木愛や畑岡奈紗は50、54、58度と、きれいな4度刻み。
上田桃子、申ジエ(韓国)に至っては50、54、60度という男子顔負けの組み合わせ。これは2人がアプローチ巧者だからこその60度というチョイスかもしれないが、渋野日向子のように52、56度という2本体制は本当に減った。興味深いのは飛ばし屋だけでなく、平均的な飛距離の選手も続々と4本体制を敷いているということ。
ダンロップのツアー担当である引地氏はこのウェッジ4本体制化の波はトラックマンの影響が大きいという。「正確な弾道測定器が出てきたことで、我々も“こことここの距離が空いていますよね”などといった説明がしやすくなりました。“今回のコースならこの飛距離のクラブは抜いてもいいのでは”といった提案もしやすくなり、ウッドやUTを抜いたぶん、下の番手が厚くなっているのが1つの理由だと思います」と話す。
どの番手構成が多いのか聞いてみると、「弊社の契約プロの方々では50、54、58度が多いと思います。グリーン周りのアプローチは基本的に58度、というプロが多く、PWとその58度との間の距離をどう埋めていくかとなると、この組み合わせが多いですね」とのこと。
フルショットのほうが距離を合わせやすく、アマチュアにとっても魅力的なウェッジ4本。とはいえ、グリーン周りのアプローチで52度も使いたい…、など、どういった構成にするのが自分に一番合っているのか悩みどころでもある。一方で丹萌乃のように「パー3も伸びているのでどれも抜けない」と飛距離がほしいゆえに、上の番手を厚めにせざるを得ないパターンもある。プロコーチ&クラブフィッターの筒康博氏に、ウェッジを何本入れるかを含めて、どうすればアマチュアは自分に合った構成が見つけることができるのか聞いた。
筒はまず、アイアンとウェッジの関係が時代の分岐点に来ていると説明する。「いわゆる『飛び系アイアン』が定番化した現在において、“ウェッジ”というクラブの存在理由を刷新するタイミングに来ているのかな?と思います」。元々はショートアイアンより短い距離で様々な状況に対応する事がウェッジの主な役割だった。だが、現在はそれに加えて、コースを攻める際の使用頻度の高い場面を想定したクラブセッティングの主役の一つになりつつある。
ただ、ウェッジが増えたということは一概にアプローチのバリエーションが増えるということにならないのが難しいところ。「3〜4本のウェッジ体制といっても、すべてのウェッジをグリーン周りで使用するプレーヤーは多くありません。PWがアイアン化してから随分時間が経っていますが、ウェッジ体制の中に侵食してきたと考えていいと思います。つまり、“フルショット”メインのウェッジと“アプローチ”メインのウェッジがチーム化していくならメリットになります。すべてのウェッジをグリーン周りで使う事は理想ですが、選択肢が多いぶん、迷いや技術が返って複雑になってしまうデメリットを感じる人もいるかも知れません」。選択肢が増えて逆に迷いも、というケースも多々見受けられる。
「例えば『振り幅は腰から腰…』のように、自分なりのルールを作ってアプローチに望むならウェッジの4本体制は大いにアリです。微妙な振り幅やスイングで打ち分けなければいけないキャリーとランの割合を、番手を替える事で打ち分ける事が出来るのが最大のメリットです。特に最新のウェッジは、スピン性能も直進性も高くソールの抜けもいいモデルが多く登場しています。『9番アイアンで転がし…」よりも、ロフトの立っているウェッジの方がイメージを出しやすくアプローチに臨めるゴルファーが多いはずです。バンカーショットも、番手を替えるだけで遠いバンカーと近くてアゴの高いバンカーをクリアーできる可能性が高くなります」。
フルショットしかり、ハーフショットしかり。『この番手でこのくらい振ったらこれだけと飛ぶ』と明確になれば細かい打ち分けをオートマチックにできる。これこそがウェッジの本数を増やす最大のメリット。だからこそ“ルール決め”が大事となる。
とはいえ、これだけロフトが多様化した時代。「ウェッジを4本入れよう」と決めてもなかなか自分にあった組み合わせを見つけることは難しい。そこで筒が提唱するのが「まずSWをバンカーショットで決めること」だ。
「名前の通り、『サンド(砂)』ですから特に練習量が少ないアマチュアの皆さんはメインの使用目的をバンカーショットにした方がいいです。その上で、上げたい時やスピンをかけたいアプローチでも使えるようにソール形状やバウンスをチェックしてみて下さい」。ここで一考したいのが56度のウェッジ。「『56度がやさしい』と言われている理由は、ダフってもバンカーショットで距離が出しやすいことです。また、フェースを開いて使う方にとってはテクニックを使うバリエーションが大きくなるメリットがあります」。3本入れるとなると、まず58度を考えてしまうが、56度という選択肢も頭に入れたい。
次にPWの距離を把握。「そして今使っているPWの方向性を意識して打ったフルショットのだいたいの距離をイメージしてください。こうなればウェッジを『チーム』として考えたときに、まず一番飛ぶPWと一番飛ばないSWが先に決まります」。ここからあいだの番手を決める際、『3本体制』になるか『4本体制』になるかを決めていく。
「ロフトを調べてきっちり距離の階段を作り、スイングをシンプルにしたい方は『4本体制』が向いていると思います。結果として、10〜12ヤードピッチになると思います。一方で『3本体制』でいきたい方は、例えば『100ヤードは〇〇度でフルショット』のように自分のイメージを重視した方が、結果としてウェッジチームが機能しやすいと思います。グリーン周りも決まった番手で使いこなせる方も『3本体制』からスタートしてみてはいかがでしょうか?」(筒)
最後に一つ注意点がある。「『3本体制』、『4本体制』どちらでも、ウェッジをチームとしてみた場合の役割はそれぞれ異なります。目的が違う以上、モデルやソール形状、バンスが番手ごとに違ってくるのは当然です。ただし、ロフトに対して長さと重さが逆転しないようにだけ注意して購入して下さい」。
解説・筒康博(つつ・やすひろ)/プロコーチ・フィッター・クラフトマンとして8万人以上のアドバイス経験を生かし、現在は最先端ギア研究所『PCMラボ』総合コーチ、インドアゴルフレンジKzヘッドティーチャーを務める。ALBA本誌ギア総研をはじめ様々なメディアでも活躍している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>