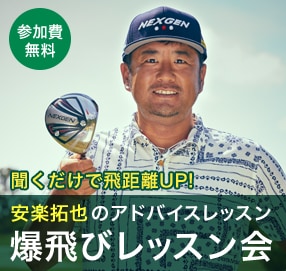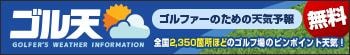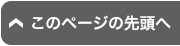「全米オープン」最終日は大混戦となり、一時は首位から1打差までに10人がひしめく競り合いで、誰が抜け出すのか、予想すらつかない状態だった。
だが、それぞれの選手の流れは少しずつ変わり始め、流れが変わるとき、そこには多くの場合、バンカーがあった。
首位タイで最終日を迎えたラッセル・ヘンリー(米国)は出だしからガードバンカーにつかまってボギー発進。6番からは3連続ボギーを喫し、優勝争いから、ほぼ脱落。7番でも8番でも彼はバンカーにつかまり、スコアを落としていった。
前半で3つスコアを伸ばし、一時は2位タイまで浮上したブルックス・ケプカ(米国)は、しかし、パー3の16番でティショットをバンカーに入れ、ボギーで後退。18番でもグリーン脇のラフから目の前のバンカーへ入れてボギーの締め括り。優勝争いからの完全なる脱落となった。
8番のバーディで、ついに単独首位に躍り出て大観衆を狂喜させたブライソン・デシャンボー(米国)が、11番、12番で連続ボギーを喫した原因は、バンカーではなくショット、パットの乱れだった。だが、13番ではガードバンカーからの4打目でグリーンを大オーバーさせてダブルボギー。左のペナルティエリアに打ち込んだ17番では、4打目を打つ際の足がバンカーにかかり、またしてもグリーンを大オーバーさせて、ダブルスコアの「8」を叩いた。
今年の全米オープンの舞台、トーリーパインズはムニシパル(公営)ゆえ、チャンピオンシップコースとはいえ、そもそもはアマチュアや一般ゴルファーのためにつくられたものだ。しかし、今大会開催を睨んで改修が行なわれ、数多くのバンカーを、アマチュアではなく世界のトッププレーヤーたちが苦しむ位置へ移したそうだ。
開幕前、トーリーパインズの難しさは「7652ヤードの長い距離だ」、「狭いフェアウエイだ」、「深いラフだ」、いやいや「硬いグリーンだ」と取り沙汰されていた。だが、サンデーアフタヌーンに選手たちが一番翻弄されたのは、つかまりやすい位置に置かれたバンカーだった。
バンカーは英語では「サンド・トラップ」。直訳すれば「砂のワナ」だ。その名の通り、トーリーパインズのサンド・トラップは勝利を目指す選手たちの足をすくうワナだった。
バンカーにつかまったからと言って、それが敗北を意味するものでは決してない。バンカーは、あくまでもワナであり、選手を乱れさせよう、狂わせようと嫌らしい誘いをかけてくる悪魔の誘惑にすぎないはずなのだ。
そう、バンカーにつかまったことが、そのまま敗因になるわけではなく、バンカーにつかまったことをどう捉え、どう対応するか次第で、多くの選手はワナにまんまとはまり、敗北への道を進むことになった。
だが、「たとえ何が起ころうともポジティブに捉える」と心に決めて実践していたジョン・ラーム(スペイン)は、大詰めの17番ではフェアウエイバンカーからピン5メートルに付け、スネイクラインを沈めてバーディ獲得。18番はグリーン右のバンカーからピン方向ではなく出せる方向へきっちり出し、5メートルを沈めてバーディフィニッシュ。
終わってみれば、それがラームのウイニングパットになった。
2週間前の「メモリアル・トーナメント」では6打差の単独首位で3日目を終えた直後、PCR検査で陽性判定が出たことが告げられ、即座の棄権と10日間の隔離を余儀なくされた。全米オープン出場も危ぶまれたが、それでもラームは前向きな姿勢を取り続けた。
「コロナは現実だ。幸いにして家族はみな無事で、僕も陽性とはいえ無症状だったことに感謝した。そうやって人生では何だって起こるのだから、ゴルフでも何だって起こりうると信じ、自分を信じて前を向いてきた」
そんなラームのポジティブな姿勢は、どんなバンカーがどこにあろうとも、もはや意味をなさなかった。
「僕はトーリーパインズを愛している。トーリーパインズは僕を愛している」
なるほど。コースに打ち克つとは、こういうことを言うのだろう。全米オープン史上初のスペイン人チャンピオンは、圧巻の勝ち方を披露してくれた。
文/舩越園子(ゴルフジャーナリスト)
<ゴルフ情報ALBA.Net>