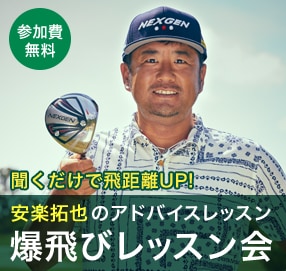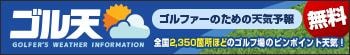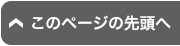2月21日から4日間の日程でシンガポール・セントーサゴルフクラブにて開催された「アジア・パシフィック女子アマチュア選手権」は、日本女子にとって大きな意味を持つ大会だったといえるだろう。
【動画】出場7名のアマチュアが自身の強みをセルフ解説
男子では、松山英樹が2連覇した「アジアパシフィックアマチュア選手権」が継続開催されているが、2018年からは女子大会が創設。男子では優勝者に「マスターズ」出場権が付与されるが、女子は「ANAインスピレーション」「全英リコー女子オープン」のメジャー2大会の出場権を手にすることができる。アマチュアにとっては非常に魅力的な大会で、19、20年大会は日本のザ・ロイヤルゴルフ倶楽部(茨城県)で開催されることも決まっている。
第1回大会に出場した日本勢は、ナショナルチームから西村優菜(大阪商業大学高校2年)、稲見萌寧(日本ウェルネス高校3年)、吉田優利(麗澤高校2年)、佐渡山理莉(名護高校2年)、古江彩佳(滝川第二高校2年)、安田祐香(滝川第二高校2年)。1月の「オーストラリア女子アマ」を制して招待選手となった山口すず夏(共立女子第二高校2年)を加えた7名がアジアオセアニア地区ナンバー1を懸けて戦った。その中で西村が72ホールを消化してトータル8アンダー・首位タイとなり、プレーオフに進んだが、惜しくもタイの15歳、アタヤ・ティティクルに敗れて、2位となった。
優勝まであと一歩まで迫った西村以外にも、安田の5位タイのほか、日本勢の多くはトップ10圏内で大会を終えた。これだけ日本勢が優勝に迫った理由は、大会前の取り組み方に工夫があったから。明確なテーマを持って、大会に挑んだ結果の効果だった。
■ プレーオフでは150cmの西村が最も的確なプレーをしていた
ナショナルチームを統括するガース・ジョーンズヘッドコーチは、「(フィールドを見て)勝てるチャンスがかなりあるなと思い、試合前の準備にフォーカスして選手とともに取り組みました。練習ラウンドでは、戦略を立てるための情報を集め、全員がその計画にしっかり向き合ったことで、2名が優勝争いに加わることができました」と総括する。
西村、安田がジョーンズ氏から試合前にかけられた言葉は“メモと向き合え”。「練習日が一番疲れましたね(笑)」という西村のヤーデージブックにはきっちりとコース戦略が書き込まれており、大会後には「自分の立てた計画を実行でき、毎ラウンド安定したスコアでプレーできたことは自信に繋がりましたし、今後の強みになります」と、優勝を逃した悔しさを持ちつつも、手応えを感じていた。
西村とプレーオフを戦ったのは、ティティクル、サソウ・ユウカ(フィリピン)、ウェンユン・ケー(ニュージーランド)。3名の経歴を紹介すると、アタヤは昨年7月、14歳4か月で出場した「タイランド チャンピオンシップ」で欧州女子ツアー史上最年少優勝を果たした逸材。日本とフィリピンのハーフで日本ツアー出場経験もあるサソウは18年1月の「フィリピンアマチュアオープン」で勝利。ウェンユンは、米国のワシントン大学で16年の「NCAAチャンピオンシップ」を制している。
プレーオフは373ヤードの18番パー4。身長160cm後半で250から260ヤードを飛ばす3名に対して、150cmの西村は飛距離で劣り、当然セカンドオナー。だが、確実なパーオンと勝負強いパッティングで2ホールをパーでしのぎ、4人の中で最も安定したプレーを見せていた。サソウ、ウェンユンが脱落し、ティティクルとの一騎打ちとなった3ホール目は、12番の441ヤードパー4。飛距離のアドバンテージにより敗れた格好だが、持てる力を発揮し、全力でコースに向き合った姿勢は賞賛に値する。その証拠に、表彰式で小柄な日本人が4日間連続“69”を出したと発表された際は、各国選手・チーム関係者から惜しみない拍手が送られた。
■ ガース・ジョーンズ コーチが語る準備の大切さ
ジョーンズコーチは、西村について「クレバーでアカデミック。コース外を含めて繊細なゲームプランを構築するタイプで、飛距離がないぶん“フェアウェイのどこにつけられればいいか”の戦略づくりが、非常に得意で質が高い。加えてパッティングも強み」と評するが、西村いわく、17年にナショナルチーム入りした以前、以後では「準備の質はまったく変わりました」と、効果てきめんだ。
15年10月よりオーストラリアのナショナルチームコーチから、日本のヘッドコーチに就任したジョーンズコーチが目指す“技術以外の準備の質を高める”取り組みは、17年からより高いレベルになっているという。
「ほとんどの選手はテクニックに関して敏感です。それはもちろんいいことですが、あくまで一つのエレメント(要素)。テクニックについて極端な話をすれば、なんとなくピン方向に球をもっていければ、勝負になります。高いパフォーマンスを維持するためには、テクニックだけでなく、心理学やスポーツ医学も同じくらい大切なもの。日本の選手は、緻密な練習ラウンドによって、試合中はストレスフリーな状態をつくれたはず。スイングの感触が悪くても、それが単にさまざまな理由の一つと捉えることができれば、パニックは起きません」
JGA(日本ゴルフ協会)には、ジョーンズコーチ就任前にもスポーツ医科学の専門家はいたが、選手のパフォーマンスに繋がる形に落とし込むまでには到達していなかった。それがジョーンズコーチ就任後、着実に進歩を果たし、ここ1年でプログラムとして機能してきている。
今大会、準備面での成功を実感したジョーンズコーチが改善点として挙げたのがハイドレーション(積極補水)。「暑熱環境で戦うときにコンディションをもっと意識しなければなりません。フィジカルコンディションの管理はまだまだ改善できます。男子チームでは、17年11月のノムラカップ(23の国と地域から代表者で争われるアジア太平洋アマチュアゴルフチーム選手権)でスポーツ医科学チームと連動した取り組みが事例としてあります。マレーシアの暑熱環境に対応するため、起床直後とラウンド後の1日2度、尿検査と体重計測を実施し、尿比重を見て、いかに脱水症状になっているかを示しました」。
■世界を席巻する韓国、急成長のタイに負けないために
米国女子ツアーを席巻する韓国勢、そしてタイもジュタヌガーン姉妹の活躍で急成長国になりつつある。今大会に出場したタイ選手もティティクルだけでなく、飛距離のポテンシャルの高いメンバーがそろっていた。日本が各国と対抗するためにも吸収すべきことはまだまだ多くあるといえそうだ。
「韓国は強いし、タイも強くなっている。欧州の取り組みも進んでいます。知識を伝えるには、若ければ若いほどいい。例えば、西村さんのような賢い選手に伝えると、積極的に自ら始めますし、それは畑岡さんも同じでした。もちろん長いキャリアのなかでは、スイングの課題が、絶対的な要因となる時期はあります。ですが、メンタル的な問題で、自信を失っていることでスイングを悪くしているのかもしれない。加えて水分摂取量が足りないとさらに悪化する。さまざまなエレメントを統合した上で選手としての土台をつくれば、テクニックだけにスコアの理由を求めなくなる。いまのナショナルチームのメンバーにはそういう選手になって欲しい」
一世代前にナショナルチームに在籍していた、畑岡奈紗、勝みなみ、新垣比菜らが、プロツアーでセンセーショナルな活躍を見せていただけに、17〜18年チームは、相対的に小粒に感じられるが、ジョーンズコーチは同等以上に強くなれると信じているという。
「畑岡さんを例にすると、彼女は、米国で世界NO.1になりたい、という決意がある選手でした。畑岡さんの土台の話をすると、連覇した『日本女子オープン』では、練習後にメディア対応をしたあとも、体のトレーニングを欠かさず、ケアを含めて、1時間半程度のメンテナンスをしていました。ほとんどのプロはそこまで綿密なプログラムは行っていなかったと思います。今のナショナルチームの選手たちはまだ彼女のレベルに達していませんが、指導する基本的な概念は変わりません。畑岡さん、勝さん、新垣さんは強い選手でしたが、その世代以上に彼女たちと接する時間があり、プロになっても活躍できる根拠が見えてくるはずです。真摯に取り組む選手たちには、ゴルフに対する敬意があると思いますから」
ゴルフに対する敬意を象徴するシーン。安田は、スタートホールのティグラウンドで90度近いお辞儀をした。西村は正規の72ホールを終えて、スコアカード提出場に向かう際、コースに向かって深々と挨拶をした。日本勢のみが行っていた「礼」は、海外で見ると新鮮で誇らしい姿だった。
<ゴルフ情報ALBA.Net>