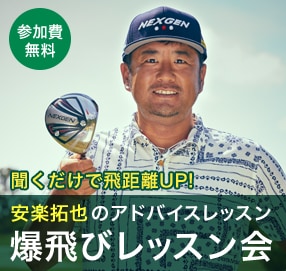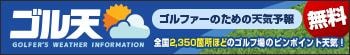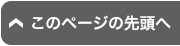ゴルフツアーに今、一番求められていること。それは“ファンファースト“だろう。
プレーヤーファーストではなく、スポンサーファーストなどでももちろんない、ファンファースト。それこそがプロスポーツイベントのあるべき姿だ。
フィル・ミケルソン(米国)が5年ぶりに優勝したWGC-メキシコ選手権では、18番を囲んだ大ギャラリーの多くがスマートフォンで撮影する姿が目立った。ツアー会場での撮影は、許可を得たメディア以外、絶対禁止だった頃と比べると隔世の感がある。だが、時代は変わった。世の中では、スマートフォンのない生活が考えられないほどに、生活の隅々にまで普及している。それに伴い、デジタルカメラ、スマートフォンのカメラも広く普及し、撮影そのものが気軽なものになった。興行もSNSなどにアップしてもらうことによって、その宣伝効果は計り知れないものがある。海の向こうでは、ゴルフでも試合そのものに支障がなければ受け入れるというスタンスに変わってきている。
日本ではどうだろう。男子は遅ればせながら、昨年から一部箇所での撮影を許可している大会もあり、限定的でも撮影解禁の方向性を打ち出している。しかし、女子ツアーは相変わらず開幕戦から撮影禁止の看板があちこちに立てられ、検討しようという話も聞こえてこない。
もちろん、米国と日本では事情が異なる。日本では盗撮防止を目的にシャッター音が鳴るのが基本だから、アプリをインストールしたりする手間をかけないとプレーの邪魔になる。気を使っているギャラリーとそうでない者を区別するのは大変だ。だが「ギャラリーに、より楽しんでもらうために」ということを大前提に考えれば、できることはいくらでもあるのではないか。
いつでもどこでも好きなときに撮影し、被写体には何の断りもなく、何でもかんでもSNSにアップデートする風潮に、全面的に賛成するわけではない。撮影されない権利も大切にするべきだ。しかし、プロスポーツは興行としてこそ成立する以上、これまでのままでいいはずはない。
国内バスケットボールのBリーグではホームページに、「試合中の写真撮影および15秒以内の動画撮影は個人での利用を目的とした場合に限り可能です」と明記されている。激しいプレーのスポーツと、”静”の部分が多いゴルフを同じように考えることはできないが、ファンサービスの方法はいくらでもあるはずだ。
“ファンファースト”意識の不足は、こんなところにも顕著に表れている。男女を問わず日本の選手の多くが、優勝スピーチで「○○(スポンサー)様、△△ゴルフクラブのみなさま、ボランティア様、そしてファンの皆様、ありがとうございました」とコメントする。違うだろ! 〇〇よりも△△よりも、最初に礼をいうべきはファンのはず。仕事でも何でもないのにプレーが見たい、選手が見たいという気持ちで時間とお金を使い、コースに足を運んでくれた人によって会場の雰囲気はつくられる。テレビを見てくれている人も同じ。それをとにかく大事にしないことには、興行性など上がらない。ツアーや先輩プロから代々伝わるあいさつこそが、「賞金を出してくれるスポンサーこそ一番大事」という意識を表面化させている。
ツアー関係者、そしてスポンサーの中にも勘違いする人間は想像以上に多いが、見てくれるファンがいるからこそスポンサーもつく。これを決して忘れてはならない。
試合数が戻らず危機感を抱く男子ツアーだけでなく、今は試合が多く人気もある女子ツアーも、20年後の姿を決めるのは“ファンファースト”をどこまで徹底できるかにかかっている。(小川淳子)
<ゴルフ情報ALBA.Net>