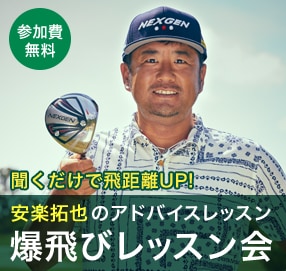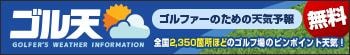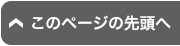『コロナ禍の環境に学ぶ 自粛を経て記録向上』(47NEWS 地方紙と共同通信のよんななニュース)。こんなタイトルのコラムに、大きくうなずき、何度も読み返した。陸上400メートルハードルのオリンピアン、為末大さんが書かれたものだ。
「陸上の世界でも大会が中止になっているが、中高生を中心に新記録が続出している」という状況を分析している内容のものだ。元々、日本は練習過多だったのがコロナ禍によって抑制され「競技をしたくてしょうがない」状態になったこと。一定期間、競技と離れたことで体がリフレッシュされ、いい状態でトレーニングや練習ができることなど、いくつかの理由が挙げられている。ケガのリスクも減っていると言う。
どの競技においても、日本のスポーツ界はいつまで経っても“スポ根“体質から抜け出せない。ゴルフの世界も例外ではない。
トップアスリートになるためには、人並み外れた練習をしなくてはならないのは当然だが、故障するまでやるのが正しいとは決して言えない。特に、体が出来上がらない子供のうちからの練習過多は、選手生命だけでなく、将来の日常生活にまで影響を及ぼす故障につながる場合もある。指導者(時には保護者)が、これを強要する例は枚挙にいとまがない。
ジュニア時代からひたすらゴルフばかりして、故障しやすい体になってしまう選手は少なくない。トレーニングを取り入れていると言ってもなお、プロになる頃にはすでに故障を抱えている選手が珍しくないほどだ。
為末さんは「競技をやりたくて仕方がない」という気持ちがいい方向に出ているとも書かれている。
ゴルフの世界ではどうだろうか。シーズン中は毎週、試合があるのが当たり前の状況だった女子プロたちは、試合がなくなってみて「早く試合がしたい」という強い気持ちを持った。試合のありがたみを改めて感じたプロも多い。ポツリ、ポツリとおこなわれている試合に新鮮な気持ちで臨んでいる。こうした気持ちを味わったことは決してマイナスにはならないはずだ。むしろ有意義な時間を過ごした、と思えれば、この先への財産となる。
ジュニア時代、学業も含めた学校生活や、家族でのごく当たり前の日常よりもゴルフを優先させて過ごした者の多い、昨今の若い女子プロたち。だからこそ、ゴルフ中心ではない生活へのあこがれは非常に強い。「できるだけ長くゴルフを続けたい」という選手もいるが「早くゴルフをやめたい」という選手が多い現実がある。
プロアスリートは、競技が最優先になるのは当たり前のことかもしれない。どんな人生を送るか、どこで生活を切り替えるかも本人次第。それでも、他競技に比べて長くプレーできるトップレベルで戦い続ける可能性を、ネガティブな理由で離れてしまうのはもったいない話だ。ワークライフバランスをうまく取りながら続けていくことを、もっと考えてもいいのではないだろうか。
コロナ禍だからこそ、自分と向きあった時間を大切にしている、と口にした女子プロは、実は一人二人ではない。それが、これからの彼女たちの日々に豊かに彩ってくれるのなら、それに越したことはない。プレーそのものにすぐに反映されなくても、やがてどこかで必ず糧になるのだから。(文・小川淳子)
<ゴルフ情報ALBA.Net>